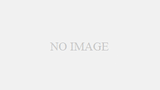Bボーイ風なフードのかぶり方をする長男
執筆本からの引用
文体は書く人の立ち位置を示すもの。生命力は文体ににじみ出る
齋藤孝著書 『原稿用紙10枚を書く力』P142から引用
1億総クリエーター時代などと言われるようになり、スマホ一台あれば情報発信はいとも絶やさずできるようになりました。一人ひとりが発信者となり、個性がその文章などに現れるようになります。その個性を現すのが、文体と一般的に言われます。1億人いれば、1億とおりの文体があるもの。
しかし、その文体を意識して書いている人はどれくらいいるのでしょうか?
決して意識しないといけないものでもありませんし、意識しなくても書けるものです。
僕自身も、「文体」という日本語そのものを知ったのは、お恥ずかしながら3週間前です。おそらくプロの方以外は無意識で使っているのではないでしょうか。
自分なりの定義
僕が定義する文体は、著者独自の世界観を現すものとしています。そこに人間味や、言葉の裏側にある奥行きなどを忍ばすことができちゃいます。できちゃうというよりも、にじみ出るという表現の方が合っているかもしれません。
この文体は、文章力<文体、という数式で表せるくらい、文章力を凌駕する力を備えているかと思います。上手な文章力を書こうとすると、大学の文学部でしっかりした知識と技術を身に着けて、出版社に勤務しているような人にしかできないと思います。
それであれば、すべての文学部で出版社勤務の人が売れる本を書けるのか、人を感動させる文章を書けるのかと言うと否です。プロの作家さんであれば、最低限の文章力はあるかと思うのですが、売れるということは、ファンが少なからずいて、買う人がいるということです。
文体に魅力があり、そこにファンが引き寄せられるのです。だからこそ、著者独自の世界観をかもしだせる=文体、をご自身でも把握していて、しっかりそれを表現できているのではないでしょうか。
文体の精度を高める方法
僕が以前まで間違っていた方法は、自分の器を広げようとしたことです。もちろん、大きなことに挑戦することでの成功体験や失敗体験は大切なことです。しかし、自分がトランプ大統領のように奇抜になることで、大統領を目指すのは違うと思います。
器を広げることではなくて、自分の器の範囲を知ることが重要です。その「際」まで自分を深堀りしたり、客観視することを繰り返すのです。それが、文体の精度を高めることにつながります。
20の器を無理に、500の器にすることよりも、20の器の中で、18や19まで水を満たすかのように、フルに活用することが、自分の役割をこなせる、そう感じることがここ最近ありました。
きっと、人間の内側にあるものが人柄ににじみ出るように、文章にもにじみ出ちゃうのではないでしょうか。
まとめ
人を引きつける文章を書く人に、人間的魅力を感じさせられます。それと反対に、酒好き競馬大好きのC・ブコウスキーという人間として終わっているような執筆家もいます。最初は嫌悪感を抱いたのですが、なぜか読み続けている自分がいました。嫌なのに読んでしまう。まさに、ブコウスキーさんの世界観に入り込むと、人間らしさ、みたいなものを教わりホッコリする自分もいます。何か人生で、大切な落とし物をしてきたのではないか、と考えさせられました。
両者に共通することは、文体が素敵です。僕にとってとても素敵な文体なのです。人間同士も好き嫌いがあるように、本にも相性があると思います。それは、文体との相性とも言えると思います。
そのように文体を意識して読んだり書いたりすると、読み進められない本は無理して読まなくても良いと自分を許せるようになりました。文豪が書いた名著と呼ばれる本を、手を付けないできたことにコンプレックスがありましたが、きっと時期が今ではないだけです。相性が合わないことに気にかけることよりも、貪ってしまうような本を遠慮なく読み進めるのも一向です。
それでも、読まなくては、と思う人には1年に1冊、自分が選ばない本に挑戦してみてはいかがでしょうか?