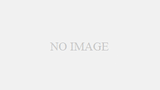あるスタッフの対応に、感動して記事にしたいと思いました。
利用者の状態を正しく知る
Aさんはもしかしたら、腰が痛いのかもしれない。
Aさんは、「腰が痛いです」と言ってきた。
2つの違いは、自分が推測することと、事実の違いです。
自分の推測とは、美味しそうなりんごがあった、など形容詞がついたり、人によっては変わることです。
それに対して事実とは、2つのりんごがあった、など誰が見ても同じ解釈となることです。
スタッフの特徴にもよるのですが、推測と事実を混在しているケースがあります。
実は、事業所の改革を進めるにあたり、このようなことから取り組んでいます。
特に新人研修やスタッフ研修に非常に有効的です。
◯◯した
△△だった
など、事実を捉えることは非常に大事です。これを間違えると、スタッフの対応も間違えてしまうので、明確にしておくことがのぞましいです。
スタッフ間の情報共有も、それが推測なのか事実によって、共有内容が変わります。
どのようにスタッフが対応するかで、利用者さんは笑顔になる
今回の事例では、Aさんが腰痛持ちだったことで長く作業をできないので、
改善するための対応でした。私には神対応だと思いました。
県病院で検査を何度もするほど腰痛持ちの利用者さん。
背が高いこともあり、机の作業が前かがみになることも、痛みが悪化する原因でした。
でも、作業をしたいが、腰は痛い・・・と悪循環でした。
あるスタッフが、ほんの少しの工夫として、大きなダンボールを2つ重ねて机の高さを補ってくれたのが、今回の写真です。
これを作ってくれたあとの利用者さんの笑顔が印象的でした。
「これなら、かがまないで作業できるから、楽!!」と満面の笑み。
支援をするってなんだろう
実は、この日の朝、私は間違った対応をしていました。
「Aさん。そんなに腰が痛いなら、1日仕事しないで、半日にする?」と言ったところでした。
しかし、Aさんは作業内容を調整しながらでも1日仕事をしたいとのこと。
私は、腰が痛い⇒休ませる、という対応をしました。
しかし、スタッフは、腰が痛い⇒軽減して作業をしやすい環境をつくる、という対応をしました。
後者のスタッフの対応こそ、支援をするってことです。
利用者さんが働きやすい環境つくりをすることが、支援なんだと肌で教わりました。
このダンボール補助机があることで、利用者さんは働きやすい環境を得ることができました。
支援するって、直接何かを手伝うことではない。利用者さんが率先して働きやすい環境整備、とも言い換えられると感じました。
まとめ
支援の対義語は介護です。
以前の延岡事業所は、車の乗り降りの際、扉の開け締めをスタッフがしていました。しかし、これは介護です。
私達は、就労継続支援B型事業所です。働く訓練所です。
だからこそ、直接何かを手伝うことではなくて、環境整備に力を入れる必要があります。
馬を川に連れて行くことはできるが、水を飲ませることはできない、という故事を聞いたことがありますが、まさにこのことが支援の根幹です。
あなたにとって支援とは何ですか?
■長男&長女日記(2歳6ヶ月&0歳8ヶ月)
長男は、目をつぶって歩いたりご飯を食べたりします。まさに座頭市。僕が大笑いするせいか、調子にのって目をつぶる頻度が増えます。
長女は、寝たあとにすぐ泣いて、添い寝を求めてきました。何歳までパパを必要としてくれるのか?とふと考えちゃいました。今この瞬間を楽しむことにします。
■1日1%の成長
村上春樹さんの「職業としての小説家」を読んで、書籍のタイトルと項目だしをする
書籍のカバーデザインを考える(迷路案)