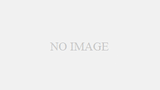写真は、美味しかったお弁当。彩りが素敵でした
なぜ、読めるようになった方が良いのか?
前回に引き続き、貸借対照表についての記事です。
経営者は、読めないよりかは読めた方が良い、というのはあります。
しかし、税理士や経理担当者でないかぎり、細かく把握する必要は無いと思います。
できれば、簿記3級程度の理解度があると良いとは思いますが、多忙な経営者にはなかなか難しいものがあります。
そのため、6回にわけて、貸借対照表の読み方を勉強することにしました。
第1回目 なぜ、貸借対照表を読みたいと思ったのか?
第2回目 重要なポイント 自社のケース
第3回目 ここまで理解できればOK 他社のケース
第4回目 応用編 銀行はここを見る
第5回目 応用編 税務署はここを見る
第6回目 まとめ 5回の勉強会の総復習
内容は上記となりました。
1回目は、すぐに貸借対照表について話す前に、目的を明確にすることにします。
理由は、目的が明確であれば、これからの内容も絞って勉強をすることができます。
それと反対に、目的が曖昧であれば、内容もあやふやなものになります。
経営者は、税理士のように数字に強くなることが目的ではないはずです。
例えば、銀行と話せるようになって資金繰りに困らないようになりたいや、
自分自身で自己分析できるようになりたい、そのような理由があると思います。
前置きが長い。前置きが大事だから
一緒に勉強する経営者は、
「ちゃっちゃっと貸借対照表を読めるように教えてくれればいいんだから」と内心思っているはずです。
でも、僕の前置きは長いです。
とても長いです。もしかしたら、1回目の勉強会は、数字の話をしないかもしれません。
それほど、前置き、前段階が重要だからです。
>なぜ、貸借対照表を読みたいと思ったのか?
ここを言語化すれば、ほぼ貸借対照表も理解できたも当然だと思います。
なぜなら、今回のサムネの写真のお弁当のように、貸借対照表も、彩り満載だからです。
貸借対照表には、経営者・社内幹部・金融機関・税務署、それぞれ見る視点が違えば、重要視するポイントが変わります。
貸借対照表には、あれもこれも、ぎっしり詰まっているからです。
まとめ
貸借対照表が難しい原因のひとつが、対象者を複数とした書類だからです。
対象者とは、利害関係者のことです。経営者・社内幹部・金融機関・税務署など。
数字に入る前に、なぜ、それを読むのか?を明確にしておけば、非常に入ってくる数字を限定することができ、整理しやすいことがポイントになるでしょう。
あなたは、どのような目的でその貸借対照表を見てますか?