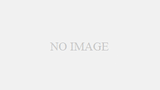写真は、先日父からもらった広辞苑。
中学生依頼に辞書を引いた
基本的にわからないことがあれば、Google先生に聞くことが一般化しています。
僕も大半のことをGoogle先生に聞くことで、知らないことを解消しています。
ある小説家の一節に、「辞書を手元に置いて引く癖をつけなさい」との言葉がありました。
なぜか、数日経ってもその言葉が引っかかり、辞書を手に入れようと思いました。
いまさら新品な辞書を買うのにも抵抗があり、ふと脳裏をよぎったのは、父がよく枕に使っていた辞書のことでした。
なんとなく、もう使わないだろうと思い、実家に行った時に聞いてみることにしました。
案の定、字を読むのが負担になってきたとのことで、押し入れでホコリをかぶっていました。
定価6,000円の辞書を無料でゲットです。
感興と書いて、カンキョウと読む
感興:興味を感ずること。面白がること。また、その興味。「ーをもよおす」「ーをそがれる」「ーがわく」
【広辞苑 岩波書店 第四版より】
いま呼んでいる村上春樹さんの本に何度も出てくる言葉です。
日本人は、漢字とその雰囲気、前後の文章から意味は理解できることが大半です。
それによって、身についている言葉の方が多いと思います。
この言葉もイメージは分かったのですが、初めて出会った言葉です。
辞書を手元に置いておくことで、言葉に敏感になり始めた気がします。
現に、Google先生に聞けば良いことを、辞書を引くことで、
「頭に知識が蓄積されつつある」感覚が自己満足となっています。
デジタルツールをつかうより、自分はアナログの辞書の方がしっくりきます。
便利な世の中になっても、アナログの辞書はやはり重さもさることながら、古典的な良さが残ります。
読み方が分からないと引くことができない
執拗(シツヨウ)と字も再度引いたのですが、すぐに見つけられませんでした。
(読みはあっていたのに、結果的に自分が見落としていたことが原因)
シツオウかな?と考え直したらして、「拗」の字の読み方が気になり始めました。
結果的に、巻末の漢字の画数から「拗」の字の読み方がわかり、やはり「おう」か「よう」で合っていたことを確認できました。
シツオウを調べると「シツヨウ」へ、というリンクになっていて、シツヨウを探していると、見つけることが出来ました。
執拗:①頑固に自分の意見を通そうとすること。かたいじ。しつおう。「ーに食いさがる」②うるさくまつわること。しつこいこと。「ーにつきまとう」
たった1単語を調べるのに5分以上かかりましたが、辞書を冒険している気持ちになり、非常に面白かったです。いつまで続くかわかりませんが、しばらく辞書で遊んでみることにします。
まとめ
20代では電子辞書を使うようになりました。
30代ではスマホのGoogleを使うようになりました。
40代の今は、10代に戻りアナログの辞書をつかうようになりました。
非効率と言われそうですが、非効率に手間をかけた分、指先で覚えている感覚が残ります。
辞書を引いていると、余計な前後の語彙も目に付きます。それも楽しいことの一つです。
電子辞書では出てこないからです。
辞書を引くことで、勉強の在り方を見直す機会になりました。
効率的なことばかり考えてしまいがちですが、非効率なことにも学びの種が往々にしてあることを教えてもらいました。
あえて行っている非効率なことはなんですか?
■長男&長女日記(2歳6ヶ月&0歳9ヶ月)
長男は、従兄弟と遊んでいる時に、自分のオモチャを貸してあげませんでした。所有欲が強い一面を垣間見ました。
■1日1%の成長
辞書を引きながら読書する