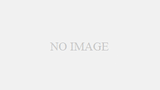写真は、スーパーに行くと必ずこのような車に乗る長男。ドアの開閉を楽しんでいる姿
苦情には2種類ある
苦情と聞くと、「ドキッ」としませんか?
その言葉には少しネガティブなイメージがあると思います。
クレームと聞くとどうですか?
日本人にはやはり苦情のようなイメージがあると思います。
正確に言うと英語では、苦情はコンプレイン。
クレームという英語には、意見や要求という意味があり、クレーム=苦情、ではないと研修の冒頭で教わりました。
冒頭でお話されるほど、すごく大事なことだと思いました。
苦情と聞くと、すごく嫌なイメージしかなく、改善しないととしか捉えませんが、意見や要求という意味があると捉えると、チャンスとも思えます。
原因も2種類
苦情やクレームが発生する原因は、個人か組織に問題があります。
例えば、暴言など吐く職員(ハラスメント)がいてクレームが発生した場合、本人の性格や資質に問題があると考えます。また、職員に適性な研修をして、してはいけないこと、と理解させる努力を組織が怠っていたとも考えられます。
これは、常に両方の視点で考える必要があることを学びました。
一方的に個人の問題ばかり指摘するのではなく、組織に改善の余地はないかと考え、
また、組織に問題があると捉えて終わらせるだけではなく、個人の責任も明確にすべきことです。
まとめ
苦情について、どのような流れで発生するかを知り、そして、どのような解決と改善方法が良いかを学びました。YouTube動画で閲覧できたのですが、2回観ました。でも、まだまだ理解が足りないなーと考えさせられます。
具体的には日頃どのようなことをするかというと、積極的にクレームを取りに行くことだと思いました。小さな不満や要求を聞くだけでも、利用者さんにとっては、気持ちを汲んでくれていると思ってもらえます。
放っておくことで、大きなトラブルの原因となります。
なにか起こる前に、日頃利用者さんと向き合う努力をしなくては、と反省したところです。