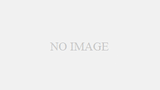写真はトラクターに乗る長男
順番は好きな方から考える
当社は3月決算なので、残すところ2ヶ月となりました。
決算賞与を支給できるか否か、必要な備品があれば当期に購入するべきかなど、考えることは多々あります。
今回は、新規採用の話が経営者からあったので、翌期予算をたてることから先にやりました。
今の人件費の昇給分と中途採用者の人件費を合算して、シミュレーションをすることで、大幅な利益が見えるようになりました。
その際に、役員報酬の増額の有無・管理職の昇給・職員の昇進も加味しました。
全員の給料を増額したシミュレーションをたてたり、据え置きのシミュレーションをしたりすることで、どのへんが損益分岐点か痛感します。
当社の場合は、労働分配率60%がひとつの指標でした。57%におさまれば、利益と返済金と余剰金のバランスが良いと言うのが以前からあり、翌期もその指標は変わりませんでした。
その指標を経営者と認識を合わせながら、翌期についての打ち合わせをしました。
決算予測は70%の精度を目指す
翌期予算の概要をつかんで、当期決算予測をたてました。
残り2ヶ月間の売上なんて、正確にはわかりません。そのため、正確な予測なんてたてられないことを前提に考えます。僕の場合、精度は70%合っていればOKくらいの感覚でいます。
なぜなら、経営者が知りたいのは1円単位の正しさより、黒字か赤字か。黒字であればいくらの納税資金がいるか、節税対策はいるか、などを知りたいからです。
例えば、税引前当期純利益が1,000万円で精度が70%であれば、実際の決算をした際に、700万円から1,300万円くらいの幅です。この間で着地することだけでもわかれば、経営者の行動は随分と変わります。
しかし、この決算予測をしない中小企業が8割以上あるのではないでしょうか。
予測をしないで、精度の高い完成品を待つのか、それとも精度が70%程度でも、2ヶ月前に分かる試作品を取りに行くのか、とちらが経営にとってよいかは、僕は断然後者が良いと思います。
まとめ
ポイントは、2ヶ月前に精度が70%の決算予測をだすことです。
このスピード感があれば、もう1回、1ヶ月前に修正するチャンスがあります。
これらを2回やるだけでも、実際の決算数値に近づくことはもちろんのこと、この2ヶ月間の経営者の行動は大きく変わるものです。
PDCAを2回まわせることにもなります。
この回転数を何回にも渡ってやることで、数字に対する不慣れが解消し、数字が好きになるきっかけになると思います。
3月5日を目処に、もう一度予測をしていきたいと思います。
決算予測はいつ頃だしていますか?