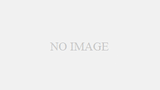写真は、県立図書館の敷地内
障がい者の意見は政治に反映されるのか
成田悠輔さんの22世紀の民主主義についての本を読んでいます。民主主義とはなんぞや、と再度考え直す提案をしています。その中で、障がい者やLGBT問題についての意見は政治に反映されやすさについて記載があるのですが、結論は「無い」に等しいと書かれています。
選挙は多数決で、多くの票を獲得した人が勝ちます。勝つとは、多くの票すなわち多くの人の理解や応援を得られたことを示します。例えば身体や精神にハンディキャップがない人は、「所得を増やす取り組み」と「障がい者が住みやすい取り組み」については、どちらに賛同するのでしょうか?
残念ながら前者になるでしょう。僕も自分ごととして前者に賛同してしまうでしょう。
少数派の意見が大事
そう考えると、どうやったら障がい者が抱えている少数派の課題を解決するのかとなりますが、本書では、アルゴリズム(自動計算)が解決するのはどうか?との提案がありました。
現実には、障がい者や少数派の意見をもっと反映させるために、障がい者や少数者が政治家になることが必要ですが、その選挙に勝つためには「障がい」という少数派の意見を多くの人に理解させなくてはいけない・・・と大きな壁があります。本当の民主主義であれば、そのような少数派の意見も加味した取り組みであるべきなので、アルゴリズムを用いることで、余すこと無く解決しようとするものです。
まとめ
B型事業所を取り巻く環境について考えたのですが、福祉の現状は障がい者とその家族が困ったことを解決して欲しいと要望してきたことの積み重ねで成り立っていると思います。そのように考えれば、少数派の意見はしっかり通ってきているとも言えます。
しかし、完成形とは言えない部分もあると思います。
上記で言いたかったのは、「少数派の意見は、優先度が低くなりがちなのでは」という素朴な疑問はどのように解決されるのだろうということです。
B型事業所は障がいある方が利用していますが、全員に共通することは網羅して解決をしていきますが、個別的な課題は解決できない場合が非常に多いです。B型事業所が解決するべきことなのか、それとも行政が解決するべきことなのか、それとも、解なし、なのか。
日々直面する課題と向き合いながら、その都度最高の解を求めていきます。
どのような課題にぶつかっていますか?
■長男&長女日記(2歳6ヶ月&0歳9ヶ月)
長男は、ニット帽をかぶってお出かけができるようになりました。
■1日1%の成長
プラレールの踏切セットのシール貼りを覚える