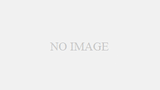B型事業所のサービス管理責任者に講義をしてもらいました。
福祉とは何かを考えることから始める
支援について考える時に、福祉とは、を考えましょうとお題をもらいました。
しかしながら、福祉の定義は、「定義なし」でした。
禅問答のようです。
なぜかというと、人の幸せには定義がないのと同じだからです。
人によって、幸せの感じ方や捉え方があるため。
例えば、手が不自由な人が、介護サポートを得ることで、お困り感が減るのが福祉だったり。また、中々仕事についても定着せず、転々とする発達障害の方にとっては、B型事業所で安定した仕事につき、再就職の練習をするのが福祉だったりします。
そのため、福祉に定義はないのです。個人の幸せは千差万別だからです。
支援と介護を比較することで、支援が見えてくる
支援とは、0.4の人が、支援員の手伝い0.6をもらって、1を得ること。
それに対して、足が不自由(0)の人が、介護者のサポートを得て抱っこして車椅子に乗る(1)ことで、1を得ることです。(ゼロイチとも呼ばれる)
支援とは、相手の状況に応じて、必要な分だけ提供するのが支援です。
上げ膳据え膳で何でもしてあげるのが支援ではありません。
以前の延岡のB型事業所では、送迎時の車の開け閉めを支援員が行っていました。利用者さんが手をはさむ事故が2度遭ったからです。
でも開け閉めは、支援ではなく、介護です。
利用者さんの9割以上が車の開け閉めをできない人はいません。
ただの介護または、幼稚扱いとなって、何もできなくなってしまいます。
自立できるお手伝いをする
大事なことは、自分でできるようにサポートすることです。
就労継続支援B型事業所という正式名称があるとおり、働くための訓練所です。
常務の発言がきっかけで、バイタルチェック(血圧や体温計)は自分で測るようになりました。
「働くのであれば、体調管理には自己責任が伴うので、自分で行った方が本人のためになる」と言われたことがきっかけです。
今までは、毎朝スタッフがひとりひとりの血圧を測っていましたが、現在は、自分で行います。自分で行うのが苦手な人は、他の利用者さんがフォローしてくれます。
実は利用者同士でフォローする雰囲気ってすごく大切にしていて、仕事中でも得意な人が不得意な人の作業を手伝うことにつながるからです。
スタッフも得意不得意があります。経理業務はその典型例ではないでしょうか。
利用者の得意を伸ばして、不得意を受け入れることが、自立するきっかけではないでしょうか。
まとめ
研修が終わった後に、今後の研修をどうするか話し合ったのですが、同じ内容を反復したいと声があがりました。
支援とは、というお題には答えがありません。
その答えがないことを、日々のB型事業所で試行錯誤しています。
その試行錯誤を立ち止まって検証する時間をこの研修の場にしようとの意見でした。
定期的な場を設けることで、スタッフ間の情報共有や思考のプロセスも研いでいきたいです。
あなたにとっての支援とは何ですか?
■長男&長女日記(2歳6ヶ月&0歳8ヶ月)
長男は、好きな絵本がだいぶ偏ってきました。繰り返し同じ本を読めるって素敵です。
長女は、おむつ替えようベットから落ちてギャン泣きしました。首とかに異常がなくホッとしました。
■1日1%の成長
15分、10年後の働き方について、ぼーっと考える時間を作った
門川心の杜でお昼ごはんをミーティングしながら食べた