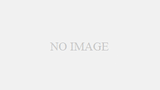延岡消防署の方にAED研修と心肺蘇生方法を教えていただきました
手前味噌ですが、心肺蘇生を行った経験があります。
今回の研修のきっかけになったのは、今年7月に利用者さんが、誤飲して心停止となったからです。
お弁当のコンニャクが喉にひっかかってしまい、呼吸困難に。
たまたま、居合わせた自分が救急車に電話して、電話しながら指示通りに心肺蘇生を行うことで、命を取り留めました。
その時は、コードブルーを観ていたこともあり、山Pさんをイメージしたことで難を乗り越えましたが、素人がやることですから、ちょっとしたミスで命を落とします。
そのことが起きたこともあり、改めて研修をしようとなり、今回に至りました。
何のための心肺蘇生方法なのか?
以前は、「心臓を動かすこと」が心肺蘇生の役割でしたが、今は、「社会復帰するために生かすこと」と再定義しています。生き返っても後遺症が残っても良くないですし、SNSによる情報拡散で、良くない状態を拡散されて居場所を失ってもいけません。
そのために、「社会復帰する」ことを考えて心肺蘇生をしてもらいたいと、消防員さんから強く教えていただけました。
また、心肺蘇生とは、生身の人間の胸を強く押します。実は、これが1番難しいとのこと。
普段したことないのに、倒れて意識がない人間に対してそのような行為をためらわずにできるのか?が大きな分かれ道になるとか。
「勇気をもって心肺蘇生をしてください。肋骨を折らないようにと指導しましたが、やはり人命優先。失敗を恐れず、勇気をもって心肺蘇生をしてください。」と何度も繰り返し指導してくださいました。
「もし、失敗して死んじゃったらどうしよう」と考えてしまうのは当然のこと。
冷静なときであれば判断できても、いざという時にできるとは限らないと思います。
私自身の体験でいうと、その場に15人の利用者とスタッフ3名がいたのですが、全員がパニックになっていたことで、冷静になれました。
なぜか、パニックな人がいると冷静になる癖があります。(逆に冷静な人がいると、自分がパニックになったり慌てますw)
あの時、119に電話して、電話口の方に、「心肺蘇生してください。やり方わかりますか?」という問いに、「教えてください」と返答して、言われたとおりにしただけです。
上手くいったから良かったものの、振り返るとゾッとする体験でした。
つかうことは、一生に一度あるかないか。
この心肺蘇生は、素人の人は一生に一度あるかないかとのこと。消防員さんは仕事のため行いますが、素人には日常起こることはありません。だからこそ、ハードルが上がってしまうのでしょう。
一生に一度あるかないかのことを、知っていることと、知らないことには雲泥の差があります。
つかえるけど使わない状態まで高めることができていると、いざとい時に慌てないで済むような気がします。
まとめ
心肺蘇生という言葉を普段つかわないだけに、違和感がありました。
1度経験しただけに、習うことには身が引き締まりました。
この研修ですごく良かったことは、心肺蘇生をする前に行うことでした。
1 周りの安全確認
2 周囲の人への指示、119通報・AED準備・人を集めてもらうこと(応援のために)
3 呼吸確認
私が心肺蘇生をした時に漠然と困ったことは、室内だったので、1は必要なかったのですが、2の利用者さんがパニックを起こしてスタッフがテンパってしまったことでした。
119通報するにも、鳴き声がうるさすぎました。
その場の安全確保と心肺蘇生するための環境づくりのために、スタッフ1人残して全員を別な部屋に移動するよう指示しました。
正確に言うと、怒鳴るに近かったと思います。
緊急時になると人はパニックになり、動けなくなります。
利用者さんに求めるのは酷なので、スタッフに頼りたいところ。
3度指示して、利用者さんをスタッフが別の部屋に移動させ、心肺蘇生できる状態になりました。
2の「周囲への指示」は非常に大事なことだと実感しました。
しっかりと正しいやり方を教わり、もしもう一度同じ状況になった時に、的確な指示を出したいものです。
そのために、常日頃指示を出すことは意識的に行っていきます。
万が一、利用者さんが心停止した時、どのような対処をしますか?
■長男&長女日記(2歳5ヶ月&0歳7ヶ月)
長男と、土曜日恒例の温泉へ。石鹸で自分で体を洗い始めたことに驚きました。しかし、石鹸を湯船に投げるのは止めて欲しいものです。
長女は、一緒にお昼寝するもグズって中々寝つきませんでした。ママのおっぱいを飲むと瞬殺でした。やはりママの存在は偉大です。
■1日1%の成長
・パナマコーヒーを注文する(深い味わいに酸味があってスッキリ飲めた)
・鶏モモ肉のサッパリスープを作る
・ブログに問い合わせフォームを作るためのプラグインを調べる